 |
この項目では、コンピュ?タのプリンタ?について?明しています。その他の印刷機械については「
印刷機
」をご?ください。
|
| この記事には
複?の問題があります
。
改善
や
ノ?トペ?ジ
での議論にご協力ください。
|
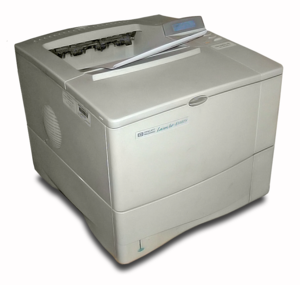 1980年代後半から普及したオフィス用レ?ザ?プリンタ?の一例
1980年代後半から普及したオフィス用レ?ザ?プリンタ?の一例
ヒュ?レットパッカ?ド
社「HP LaserJet 4100TN」
 1990年代の家庭向けインクジェットプリンタ?の一例
1990年代の家庭向けインクジェットプリンタ?の一例
エプソン
「PM-700C」
1996年
11月??
 ドットインパクト式プリンタの一例
ドットインパクト式プリンタの一例
富士通
「DL3300」
プリンタ?
(
英
:
printer
)とは、印刷用の
機械
の??である。
印刷機
(いんさつき)などの名?でも呼ばれる。
本項では特に、
コンピュ?タ
からの情報
出力
に用いる
周?機器
としてのプリンタ?について?明する。その他の印刷機械については、
印刷機
を?照。
?要
[
編集
]
プリンタ?は、
コンピュ?タ
や
ワ?ドプロセッサ
などからの情報出力?置として使用される。時代や用途に?じて多種多?な方式がある。
コンピュ?タが登場するまでは、
通信
には
テレタイプ
が使われていた。
1946年
に
ENIAC
がペンシルベニア大?で制作された。
演算
結果を出力する必要が生じ、
1947年
にテレタイプを原型とした
活字
方式のコンピュ?タ用プリンタ?が登場し、
米軍
でも使用されるようになった。
1950年代
から
1970年代
までは、活字プリンタ?や
IBM
のセレクトリックプリンタ?(下記)、
グラフ
や
?形
を描きたい場合は
プロッタ
などが主に用いられていた。1970年代から
1980年代
半ばまでは、活字方式よりも多種類の文字を印字できる
ドットインパクトプリンタ?
が主流となった。この時期のドットインパクト方式のプリンタ?は作動音が大きく、プリンタをまるごと覆う防音ケ?スなども販?されていた。また熱??方式(
感熱紙
)を用いる
サ?マルプリンタ?
も普及した。
1980年代
半ばからは、企業向けに
ゼロックス
社の
複?機
と同じ原理で細部まで印字され、音も?かな
レ?ザ?プリンタ?
が普及した。
1990年
頃から
インクジェットプリンタ?
が台頭した。家庭向けには十分な性能で比較的安?であったため普及し、
年賀?
や
グリ?ティングカ?ド
の印刷などに使われるようになった。?初は印字の品質や速度が低かったため企業向けとしてはさほど普及しなかったが、その後は技術の向上によりそうした欠点は改善され、
2008年
頃には
パソコン
用プリンタ?出荷台?の3分の2をインクジェットプリンタ?が占めるまでになった。
2000年代
初頭には、企業向けにはレ?ザ?プリンタ?、家庭向けおよび小規模オフィスではインクジェットプリンタ?、と棲み分けられる傾向が?まった。その後は個人向けの安?なレ?ザ?プリンタ?も普及した。またインクジェットプリンタ?は急速に低?格化が進み、
2005年
頃からは
コピ?
や
ファクシミリ
機能が搭載された
複合機
タイプが主流となった。
企業向けレ?ザ?プリンタ?は、
モノクロ
?機能タイプ(超高速大量印刷用や超安?印刷用など)から高機能複合機タイプまで用途に合わせた??なタイプが販?されており、また
?票
印刷ではドットインパクトプリンタ?も根?い需要がある。
印字方式による?分
[
編集
]
活字プリンタ?
[
編集
]
 デイジ?ホイ?ル
デイジ?ホイ?ル
先端に活字が植えられている。
 球面に
活字
を刻んだ「
IBM
セレクトリックタイプライタ方式」の活字セットの球。
フォント
などの?更は違った球?セットを付け替えて行われた。
通?
ゴルフ
ボ?ルとも呼ばれた。
球面に
活字
を刻んだ「
IBM
セレクトリックタイプライタ方式」の活字セットの球。
フォント
などの?更は違った球?セットを付け替えて行われた。
通?
ゴルフ
ボ?ルとも呼ばれた。
2
ユ?ロ硬貨
は大きさの比較として置いたもの。
タイプライタ?
のように、文字ごとの字母の活字を紙に打ち付ける方式である。一般的なタイプライタ?同?の腕の先端に活字を植えたものや、球面に活字を植えた「
IBMセレクトリックタイプライタ
(
英語版
)
方式」と呼ばれるもの、円盤に放射?に活字の植えられた腕を配置した
デイジ?ホイ?ルプリンタ?
、活字を環?一列にしたベルト?のもの
[注 1]
、
円柱
形の
ASR-33
など各種の方式がある。英?字のみの文書、プログラムリストの印刷などに用いられた時期があるが、印字音が大きいという欠点があり、他のプリンタ?の印字品質の向上と共に使われなくなった。方式にもよるが多くの場合、活字群のセットの英?字にさらに
カタカナ
を加えると文字?が多くなり?まらず、日本語の
ひらがな
、カタカナさらに
漢字
の印字は
ドットインパクト方式
の出現を待たなければならなかった。
活字プリンタの?史
[
編集
]
 | この節のほとんどまたは全てが
唯一の出典
にのみ基づいています
。
他の出典の追加
も行い、記事の正確性?中立性?信?性の向上にご協力ください。
出典?索
?
:
"プリンタ?"
?
ニュ?ス
·
書籍
·
スカラ?
·
CiNii
·
J-STAGE
·
NDL
·
dlib.jp
·
ジャパンサ?チ
·
TWL
(
2022年11月
)
|
活字プリンタ?の?史は古く
第二次大?
前から
モ?ルス符?
を一旦
鑽孔テ?プ
に採りそれを
紙テ?プ
に印字するものから
[
要出典
]
、
テレックス
通信(5?位
ボ?符?
)での印刷電信としては?に第二次大?前の1921年頃のMorkrum
[1]
、
テレタイプ
、
シ?メンス
、
ホイ?トストン
などからテ?プ式、ペ?ジ式活字プリンタ?が作られた。特に1930年からのテレタイプ社製15型機はタイプバ?式ペ?ジ印刷方式のもので、第二次大?中に米軍が使用し、約20万台製造された
[2]
。15型と?用された1925年からの14型機は鑽孔テ?プに印字もするもので
[3]
自動テ?プ送信のため使用され、?者が合?したものが1942年からのASR-19である(占領下
GHQ
で最初に見られたのは1949年)
[4]
。その後1951年に信?性の高い28型機 (ASR、KSR、RO) が出現し
[5]
、日本でも新聞社や放送局や
商社
で?台から十?台が24時間新聞電報を打ち出していた。
7?位
ASCII
符?を用いる1963年頃に出現した
ASR-33
がテレタイプ社から出てからは、5?位ボ?符?機は印字文字の種類の少なさから次第に使われなくなり、ASR-32とKSR-32が5?位符?機としては最後のものとされた
[6]
。ASR-33はプラスチックカバ?で覆われるなど、金?カバ?の重厚な5?位ボ?符?28型機と比較して劣るとされたが、ASCII符?のペ?ジプリンタ?としては以後標準的存在であった。
プロッタ
[
編集
]
 プロッタ?の一例。
Apple 410 Color Plotter
とその出力結果。
プロッタ?の一例。
Apple 410 Color Plotter
とその出力結果。
プロッタあるいはプロッタ?(
英
:
plotter
)は、点や線を描くことを目的とした?置である。プロッタ?部で、点や線を描くべき位置を具?的にXとYの
座標
を算出しつつ描くため「X-Yプロッタ」とも言う。
グラフ
や簡?な線?
?形
を描くのに用いられてきた?史があり、
設計?
を描くためにも盛んに用いられてきた。?初は??な制御方式があったが、次第に
HP-GL
のような?形?理言語を用いて制御するようになった。
プロッタ以外には活字プリンタ?やドットマトリクスプリンタしかなかった時代には、プロッタは綺麗な線を描?できるほとんど唯一の機器であり、?面出力用機器の標準として使用されていたが、
1990年代
後半頃からは次第に大型インクジェットプリンタ?などに置き換えられ、現在では特殊な用途以外は使われなくなっている。
描?に
ボ?ルペン
やインクペン、
シャ?プペンシル
などを記?紙に相?的に移動して作?するものを「ペンプロッタ」と呼び、
ペン
を使わず
ラスタ?
描?するものを「ペンレスプロッタ」と呼ぶ。
ペンプロッタには、記?紙を平らな台に固定し、ペンを??に移動する「フラットベッド型」の他に、?端に連?穴の開いた記?紙を
スプロケット
の付いたドラムで移動する「ドラム型」、記?紙を上下からロ?ラ?に?み、摩擦で移動する「ペ?パ?ム?ビング型」といった形式がある。いずれもペンを上下させながら記?紙に?して物理的に相?移動して作?するので、時間がかかる、動作音が大きい、使用するペンの種類によってはペン先が磨耗して線幅が安定しない、といった欠点があった。
ペンレスプロッタには、「
インクジェットプロッタ
」、「感熱式プロッタ」、「?電プロッタ」、「レ?ザ?プロッタ」、「LEDプロッタ」がある。ペンレスプロッタは、ペンプロッタの置き換え用として開?されてきたが、印刷機構的には通常のプリンタ?と全く同じであり、HP-GLなどペンプロッタと共通の制御コマンドを使用できることによって通常のプリンタ?との差別化がされていた。
Windows
の普及やプリンタ?
ドライバ
の進?によって、?面出力において制御コマンドを意識する必要がなくなり、ペンレスプロッタという分類自?ほぼ消滅した。
なお、プロッタの基本構造はそのままに、ペンの部分をカッタ?(刃物)に置き換えた、「
カッティングプロッタ
」がある。カッティングプロッタは「印刷機」というよりもむしろ「加工機」に分類される機械であり、主に
カッティングシ?ト
等を切り?くことを目的として用いられ、看板や自動車やバイクのボディ?に貼る文字や?形の作成や、衣料用
型紙
の作成など、業務用分野で今も盛んに使用されている。また
メイカ?ム?ブメント
が盛り上がるとともに、
DIY
や
自作
のための道具、シ?ト?のものを加工するための道具として、
3Dプリンタ
と同?に2010年代に個人にも再注目されるようになった。
熱??方式
[
編集
]
テ?プ
に塗布された
インク
を熱によって?象物に??する方式で、主に
熱溶融形
と
昇華型
とに大別される。
熱溶融形
[
編集
]
テ?プに塗布された
インク
を熱で融かし、
紙
などの?象物に??する。一般家庭に
パ?ソナルコンピュ?タ
が入り始めた時代には安?な家庭用プリンタ?として使われた。その後、
ワ?プロ?用機
、小型
ファクシミリ
(FAX)、ラベルプリンタ?、航空チケット印刷などに使われている。また。
デカ?ル
の印刷によく使われる。
日本では、
マルスシステム
による
切符
類や(??)航空システムにおけるチケット?行プリンタ?に長らく使用されていたが、前者は2色感熱紙の開?および低コスト化、後者はシステムの省スペ?ス?省コスト化などの理由から感熱式に移行されてつつある。
顔料
インクを用いるため、耐水性および
耐候性
に優れるが、カラ?印刷の場合色の?だけ同じ手順を繰り返す必要があり色?が?す?に印刷に要する時間が長くなり、複?回の紙送りを繰り返すため色ズレが?生しやすいという短所がある。
インクリボン
を?着せずに感熱式プリンタ?として
感熱紙
に印刷できるものもある。
インクリボンを使うタイプでは、インクリボンに印刷した?容が?るため、印刷した??(ジャ?ナル)として活用できる反面、情報漏洩の原因になることもある。
昇華型
[
編集
]
インク
に熱を加えて
昇華
させる方式で、熱量を細かく制御することでインク量の調節ができるため、
??
に近い?質を得ることが可能である。DTP用や、フォトプリンタ?、
ビデオプリンタ?
がある。原理上染料インクが使われるために熱溶融形よりも耐水性、耐光性において劣るが、近年の昇華型インクにはラミネ?ションを施すことにより耐水性?耐光性を高めたものが主流となっている。
感熱式
[
編集
]
加熱で?色する特殊な用紙(
感熱紙
)に印刷するための?置で、かつては
ファクシミリ
の出力用に感熱ロ?ル紙として?く使われていた。現在でも家庭用FAXや
レシ?ト
に多いが、耐?品性に乏しく、また、時間の?過により自然に?色や褪色を起こすという感熱紙の性質のために、長期保存に向かない。
?色?を?包した感熱性マイクロカプセルを使用する感熱紙もあり、サ?マルヘッドの熱量に?じた濃度の?色?を放出し、紫外線でジアゾニウム?を分解することにより定着する。フルカラ?の可能な
サ?モオ?トクロ?ム
や
ZINK
がある。
放電破?式
[
編集
]
導電性
の加工を施した?用紙(放電破?紙)の表層を放電で破?することで印刷する方式である。
光露光加?定着式
[
編集
]
サイカラ?
が開?した方式で
光重合樹脂
で出?た
マイクロカプセル
の?部に?色?が入っており、露光することにより硬化し、加?する事で未露光部の?部の?色?が放出され?色する
[7]
。感光波長の異なる光重合樹脂をYMCにそれぞれ使用することでフルカラ?の表示ができる。
ドットインパクト方式
[
編集
]
 印字の例。多?の点の集まりで、文字を表現。
印字の例。多?の点の集まりで、文字を表現。
 エプソン
VP-500プリンタ?(カバ?を外して撮影)
エプソン
VP-500プリンタ?(カバ?を外して撮影)
 ドットインパクト?プリンタ?Tandy DMP-133(右上)
ドットインパクト?プリンタ?Tandy DMP-133(右上)
 連?用紙を使用したドットプリンタの使用例(ロイタ?通信(ボン 1988))
連?用紙を使用したドットプリンタの使用例(ロイタ?通信(ボン 1988))
??に?べた
ドット
に??する細いピン(=針?金?)を、紙の上に配置された
インクリボン
(=インクを吸わせた?)に叩き付けて(インパクトして)印刷する仕組みである。この方式は、複?用紙への重ね印刷が可能なほぼ唯一の方式であり、完全に同一の文章を一度に打ち出すことができる。印字するインクリボンの色を切り替える機構を持つことで多色印字が可能な機種も登場した。
この方式が登場して?十年間ずっと「ドットマトリクス?プリンタ?」と呼ばれていたが、1990年代にインクジェット方式が登場?普及し、その方式もやはり「点のマトリクス」で文字を表現していたので、「ドットマトリクス」の呼?が正確でなくなり、??のインパクト式ドットマトリクス式プリンタ?を?別して呼ぶため、
レトロニム
として「ドットインパクト式プリンタ」「ドットマトリクス?インパクト?プリンタ」などと呼ばれるようになった。
打?に用いるワイヤピンは、
磁?
アクチュエ?タ
により高速で?動される。ワイヤピンは極力平坦な切?面でなければならないため、高出力レ?ザ?による切?加工が施されている。このプリントヘッドには、?放型と吸引型がある。
- 吸引型 - 印字する瞬間にワイヤピンが接合されたアクチュエ?タを電磁石で吸引してワイヤピンを押し出す方式。印字後はアクチュエ?タの?性により元の位置に?る。
- ?放型 - 印字する瞬間に電磁石に電流を流して、アクチュエ?タを保持していた磁力を打ち消し、アクチュエ?タのバネ性でワイヤピンを押し出す方式。小型で安?。
- 水平型 - 小型で8枚まで複?が可能。
- ライン型 - 業務用の大型で高?な機種。
初期のものでは1文字あたり8ピン (48
dpi
(dots per inch)、最大では48ピン (360 dpi) 程度のものまであった。
PC-8822
などの16ピン仕?の製品が登場してからは、
漢字
の印刷が現?的となった。PC-8801からPC-8822へ
漢字
の「漢字」という文字の印刷は、BASICコマンドにおいてLPRINT chr$(27)+"K" +chr$(&H34)+chr$(&H41) +chr$(&H3b)+chr$(&H7a) +chr$(27)+"H"<改行>とすることで印刷することができた
[8]
。
現在は
[
いつ?
]
24ピン (180 dpi) がほとんどである。
かつては事務用から家庭用まで?く使われた。だがドットを構成するピンを叩きつける構造のため作動音が大きく、高精細化にも限界があり、ほとんどの用途で他の方式(主に家庭用は
インクジェットプリンタ?
、業務用は
レ?ザ?プリンタ?
)に置き換えられた。その後はプリンタ?としては、
ATM
などでの記帳や複?用紙(
ノ?カ?ボン紙
等)への重ね印刷に用いられる用途がほとんどである。
しかし、他の方式のプリンタ?と比較して電力消費が少なく、またこの方式に用いる
インクリボン
は乾燥に?いという利点がある。そのため待機時間を含めた長時間作動での維持負?が少ないという利点があり、アラ?ム記?(これは連?紙を利用するという点も大きい)、アナログ式の
タイムレコ?ダ?
や各種測定器など、時間計測に用いる場合は重?される。
乾式電子??方式
[
編集
]
 Apple
レ?ザ?プリンタ?
LaserWriter
Pro 630
Apple
レ?ザ?プリンタ?
LaserWriter
Pro 630
一般的には「
レ?ザ?プリンタ?
」として知られる。?電させた感光?に
レ?ザ?
光
などを照射し顔料粉末(
トナ?
)を付着させ、用紙に??した上で熱や?力をかけて
定着
させる方式であり、これは「
?電
??」や「
ゼログラフィ?
」とも呼ばれる。
原理としては乾式の
複?機
とほぼ同じである。感光?は通常、ドラム?で、この表面を光で走査しつつ回?させ印刷を行う。感光?への書き?み光源としては、レ?ザ?光源だけでなく、
?光ダイオ?ド
(LED) を用いることも可能であり、この場合には「
LEDプリンタ?
」と呼ばれる。
消耗品である感光ドラムの耐久性を、トナ?の補充頻度に見合う程度にまで下げ、ドラムとトナ?とを一?の部品として交換する方式が主流である。その一方で、ドラムの耐久性を高め、トナ?容器のみの交換が可能な設計とすることで運用?費の低減を?る動きも見られる。
用途としては、主に業務用で利用される。業務用の複合機(複?機+プリンタ?+ファクシミリ+イメ?ジスキャナ)は、この方式が多い。
この方式のプリンタ?は他の方式と比べて構造が複?で、部品にもより高い品質が要求されるため、製造コストが高くつく。そのためかつては高?な製品であったが、急速に?格の低廉化が進んでおり、個人用としても普及している。
フルカラ?印刷
[
編集
]
この仕組みによるフルカラ?印刷には、タンデム方式と4サイクル方式がある。
- タンデム方式 - ドラムを連?し、一回の手順の中で各色(減法混合の
三原色
である
シアン
(藍)?
マゼンタ
(紅)?
イエロ?
(?)に
?
を加えた
CMYK
方式)を順次??するもので、?色印刷とほぼ同じ時間で印刷物を完成させることができる。
- 4サイクル方式 - 1つのドラム上に各色の現像機を配置し、各?色の??を繰り返すため、?色印刷に?しおおむね4倍の時間を要する。
インクジェット方式
[
編集
]
 インクジェット?プリンタ?の例
インクジェット?プリンタ?の例
キヤノン
?BJ S520
(共通設計の日本??向けBJ S500は2001年10月、BJ S530は2002年5月??)
インクジェット方式とは、主に液?、時に固?のインクを微粒子化し、加?や加熱などにより微細孔から射出させる方式で、近年、噴射孔の極微細化が著しく、このために高精細な印刷結果が得られるようになっている。また、他の方式と比して多色化が容易で、多いものでは12種類のインキを使用し、微細噴射孔とも相俟って
銀???
?みの高?質が?現されている。現在の一般家庭向けカラ?プリンタ?の主流となっている。
小型のものは、家庭用や小規模なオフィス用として利用される。家庭あるいは
小規模なオフィス
用の廉?版
複合機
(複?機+プリンタ?+
ファクシミリ
+
イメ?ジスキャナ
)も、この方式が多い。また、大型のものでは、1,000ミリメ?トル幅を超える大判用紙への印刷のできるものまであり、
XYプロッタ
からの置き換えや、巨大な
グラフィック?ア?ト
作成への?用などが進んでいる。
ほとんどの機種で使用するインクは水性インキであり、一般論としては耐水性に乏しい。技術的には
染料
系、
顔料
系どちらのインキも可能であるが、全般的には染料系インキが多い。一般的に染料系は
演色性
に優れ、顔料系は耐光性に優れるといわれるが、近年ではその差は僅かなものとされている。また、顔料系の方が紙表面でインキがにじみにくいので、特にモノクロ印刷では高精細化に向くといわれる。業務用としては、耐候性に優れた
溶?
系のインキを使用する機種も存在する。
点字プリンタ?
[
編集
]
点字プリンタ?とは、??な方式により
点字
を紙(
点字用の?用紙
である場合が多い)に出力することができるプリンタ?のことである。
??、
点字器
などを使用して、点字を1文字(6つの点で一組)ずつ紙に作り出していた作業(点字を?用紙に点筆(?筆?の器具)で打つ。表に出っ張った点がでる)を、コンピュ?タ?を使用することで手?に点字?および点字書籍を作れるようになった。具?的には、ワ?プロで作ったテキスト文を点?ソフトで?換し、点字プリンタ?へ出力と言う流れであるが、??より極めて短時間で紙へ出力できるようになった。
印刷方式は、ハンマ?ドット方式と呼ばれる方式や、特殊インク(印字すると点字の凸の形にインクが膨らむ)を使用するものや、
3Dプリンタ?
の技術を?用したものなど??な方式が有る、一番一般的なハンマ?ドット方式の場合、
ドットインパクトプリンタ?
のようにピンで?用用紙を叩いて凸をつけて点字を作る。
また、用紙の種類も連?用紙に点字を打っていくものと、?票ずつ印字していくものがあり、一般には片面印字のみのものが多いが、?面印刷ができるものもあり、?面印字の方式には表頁の行間の裏面に打っていくものと、表面の点字の文字間に裏面の点字が打たれていくものなど、さまざまなものが??されている。
叩いて打っていく方式のため、印字時の?音が激しく、防音室や防音ボックスが必要なほどの製品も存在する。
印字動作による?分
[
編集
]
シリアルプリンタ?
[
編集
]
1文字の印字指令が?るたびに現在の印字ヘッド位置に印刷する方式。
一般的には、「改行(または復?改行)指令を受信するまで印字バッファ?に蓄積し、行?位で印刷を行うことにより印字を高速化する」
#インパクトプリンタ?
を用いた方式。
メカニズム
的には、「
ドットインパクトプリンタ?
や
インクジェットプリンタ?
も、
シリアルプリンタ?方式
である」と言える。
ASR-33
など、活字方式プリンタ?をキ?ボ?ドと組み合わせた端末で一般的な方式。
技術開?により、
- 「高速印字のための行?位で印刷する方式」(→下記
ラインプリンタ?
を?照。)
- 「
スペ?ス
?
タブ
などの空白文字に相?する部分を高速で移動する」
などの機能が追加されている。
ラインプリンタ?
[
編集
]
左右に高速移動するピンを?十個配置し、インパクトにより、同時に多くの文字を印刷する方式。
1行文字?分の印字ヘッドを?列に備え、一回の印字動作で1行分を同時に印字できる
インパクトプリンタ?
のことを指す。
印字ヘッドを高速で循環させて適切な
字母
が、適切な行位置を通過する際にハンマ?で叩くことで印字する。ピン全?(ハンマバンクと?される)が左右に移動することにより文字が形成されていく。そのため、?分?百行の印字が可能である。複?を要する物で、大量に印刷を行う際などに使用される。
字母の?に制限があり、開??初は事?上
ASCII
文字と
カナ
文字程度しか印字できなかった。(もっとも、現在では改良され
漢字
印刷に耐える機種もある。詳しくは下記「
日本語ラインプリンタ?
」を?照。)
印字時に「ガシャガシャ」とハンマ?音がする機種が多い。また、この?音が比較的大きい。これを防ぐため、設計上、?置全?が箱で?まれたような構造になっていたり、防音カバ?を備えているのが一般的。
印刷ヘッドが高速で往復するインクジェットプリンタ?も、動作の上ではラインプリンタ?の一種である。
日本語ラインプリンタ?
[
編集
]
ラインプリンタ?と比較し、漢字が印字できることから「漢字ラインプリンタ? (KLP) 」とも呼ばれる
[9]
。
ペ?ジプリンタ?
[
編集
]
ペ?ジプリンタ?
は1ペ?ジ?位をまとめて印刷するプリンタ?。一般に
乾式コピ?技術
を用い、光源にレ?ザ?が使われることが多かったため、
レ?ザ?プリンタ?
と呼ばれている。
連?帳票を用いることができず、?票のみ印刷可能なプリンタ?は皆
ペ?ジプリンタ?方式
と呼ばれている。高速で?かな動作音であるが、?置やメンテナンス費用はやや高?。カラ?ペ?ジプリンタ?もある。
印字速度は、プリンタ??部でのイメ?ジ展開の性能に依存する割合が大きい。文字中心であれば短時間で出力されるが、イメ?ジ?像を出力する場合は多くの時間がかかる。値段の高いものではイメ?ジ展開を行うマイコンチップを高性能化して、高速で出力できるようになっている。その他、定着機構の性能も印字速度に影響する。
一般に、高速に印字しようとすると用紙の定着器通過時間が短くなるため、定着器をより高い?度に維持する必要があり、きめ細かな制御が必要となる。
フィルムプリンタ?
[
編集
]
連?した
ネガフィルム
または
ポジフィルム
に直接、レ?ザ?光を?てて印字する物。レ?ザ?光で感光した後は
現像
作業が必要になる。主に
新聞社
で使用されている。また、
輪?機
用の版の作成にも使用される。
制御方式
[
編集
]
- ESC/P
(Epson Standard Code for Printers)
- 1985年
頃に
セイコ?エプソン
の開?した制御方式。仕?が公開されたため、他社のプリンタ?にも採用され、また
AX
や
DOS/V
ではプリンタ?の標準方式となっている。レ?ザ?(ペ?ジ)プリンタ?用として ESC/Page がある。セイコ?エプソン製プリンタ?の「ESC/Pス?パ?」では、201PLのエミュレ?ションモ?ドもある。
- LIPS
- キヤノン
の開?した、レ?ザ?プリンタ?の制御方式。最新バ?ジョンはLIPS Vである。
- PostScript
- アドビ
の開?したレ?ザ?プリンタ?の制御方式。
マッキントッシュ
や
Linux
の標準方式であるが、アドビとのライセンス料の?係からか、この方式のプリンタ?は非常に高?(?十万 - 100万円以上)である。そのため、
リコ?
などによる互換方式も?く使われている。
- Windows Printing System
(WPS)
- マイクロソフト
が開?した制御方式で、印刷イメ?ジ展開などの主な?理を
Windows
の機能を用いてパソコン側で行うことで、プリンタ?の製造コストを下げようとしたもの。
Windows 95
の全盛期であった
1996年
-
1997年
頃に??された低?格のレ?ザ?プリンタ?に多く採用されたが、マイクロソフトとのライセンスの?係などで短命に終わり、また後?OSの
Windows 2000
や
XP
、
Vista
ではドライバの提供などのサポ?トが中止された。
- HP-GL
(Hewlett Packard Graphics Language)
- ヒュ?レット?パッカ?ド
社が開?したプロッタの制御言語(方式)。
- 201PL
- 日本電?
(NEC)
PC-9800シリ?ズ
用純正プリンタ?「PC-PR201」「PC-PR101」シリ?ズ用の制御方式。セイコ?エプソンの「ESC/Pス?パ?」や、1990年代までに製造された各社レ?ザ?プリンタ?の多くがこの201PL
互換モ?ド
を持っている。NECの純正プリンタ?には、「PC-PR」シリ?ズとは別に「NMシリ?ズ」もあった。ちなみに、PC-9800シリ?ズでは動作しないWindows XPでも、標準で「PC-PR201」「PC-PR101」「NM」シリ?ズ用のドライバが??されているため、USB?換やプリントサ?バで認識できれば利用可能である。
[1]
- 他の方式はコマンドを組み合わせることにより相互に互いをエミュレ?トできるのに?して、201PLは印刷文字幅に?じてヘッド移動速度が?化するという特性があり(さらに印刷中に文字幅が?わるとライトマ?ジンが?更前、レフトマ?ジンが?更後という非常に扱いづらい境界値にヘッドが移動する)、201PLではいったん最大解像度であらかじめレンダリングした物を出力するか、文字幅に?じて分割して出力しなければならない。この制約が存在することが逆に201PL方式の延命をもたらし、他のシリアルプリンタ?方式が衰退した現在でも??されている。
接?方式
[
編集
]
ユニバ?サル?シリアル?バス
(USB)、セントロニクス仕?(
IEEE 1284
-
パラレルポ?ト
)、
シリアルポ?ト
(
RS-232C
,
RS-422
)、
GP-IB
、
IEEE 1394
などがある。??はパラレルポ?トや、マッキントッシュではRS-422が主に使われていたが、現在はUSB接?が主流。最近は一部メ?カ?では
無線LAN
に??した機種も存在する。
ただし業務用(オフィス環境)では、??
プリントサ?バ
機能によるネットワ?ク接?(
TCP/IP
など)が主流となっており、共有プリンタ?以外でのロ?カル接?(PCとプリンタ?を1:1で直結させる方法)はあまり見られない。
また?純なネットワ?ク接?(TCP/IP接?)ではなく、共有プリンタ?形式での接?も多く用いられる。これを行うことにより、プリンタ?を接?したサ?バPCに各種OSのドライバを一括して保持させることが可能になる。クライアントとなる他のPCはサ?バPCが保持しているドライバをインスト?ルでき、個?のPCにドライバCDを渡す必要がなくなる。つまり、ドライバ管理が非常に容易になるという利点がある。
主なメ?カ?
[
編集
]
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
出典
[
編集
]
?連項目
[
編集
]
ウィキメディア?コモンズには、
プリンタ?
に?連するカテゴリがあります。